消費税を国に納めるのは事業者ですが、輸出を主たる事業とする経団連に多くいる大企業には1兆円を超える金額が還付されます。世界では付加価値税というものを日本では消費税と命名し、一見、消費税の目線では平等に見えてもこのカラクリが本質であることを知ってて無視するのか無知なのか?消費税を国に納めるのは事業者ですが、
輸出を主たる事業とする経団連に多くいる大企業には1兆円を超える金額が還付されます。
世界では付加価値税というものを日本では消費税と命名し、一見、消費税の目線では平等に見えてもこのカラクリが本質であることを知ってて無視するのか無知なのか?— パラディドル(失語症)@甲甲甲 甲乙乙 (@4hykI) July 16, 2025
消費税が本当に「間接税」で、預かり金が発生しているのなら、その理屈は成り立ちます。でも、消費税は、法律でも、取引の実態でも、預かり金は発生していません。消費税は事業者が決める「対価の一部」であり、所得税や個人事業税などと同様に、事業者が納める「直接税」なのです。
消費税法第63条(消費税額および地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格の表示)で、レシートなどへの表示が義務付けられているので、一見、消費税を価格に上乗せして支払っていると感じてしまいます。下請け業者なども、仕入れ時に納入業者に消費税を支払っていると思い込まされています。
ところが、これは全くの勘違いです。私たちが、消費税分として支払っていると思っているもの(レシートの消費税分)は、「対価(物の値段)の一部」です。これは、1990年3月26日に東京地裁、同年11月26日に大阪地裁で判決が確定しており、東京地裁の判決では「…消費税分は対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」と認定しています。
そもそも消費税は、一つ一つのモノやサービスに10%をかける仕組みではなく、事業者は、1年間分の売上高にかかる税金から、1年間分の仕入れや経費にかかる税金を差し引いて税務署に納めています。「消費者や親会社が支払った」とされる消費税分とは関係のない金額を納めているわけです。取引価格は需要と供給の力関係で決まるため、立場の弱い側が負担を強いられることになります。売り上げにかかる税金のため、景気に関係なく、中小業者は、赤字でも負担を強いられるのが消費税です。
消費税の由来にも関わりますが、日本の「間接税」の中で、輸出還付金が設けられているのは消費税だけです。かつての物品税も、外国の消費者からは税金を取れないので免税でしたが、還付金はありませんでした。近年、日本酒や国産ウイスキーなどが海外で評価されて輸出されています。酒税も輸出免税ですが、還付金はありません。さらに、医療に関わる消費税は「非課税」として、患者からは受け取れませんが、ここにも還付金はありません。
消費税だけが「ゼロ税率」と「仕入税額控除」があるために、輸出大企業に巨額の還付金が生じる不公平な仕組みになっています。
※2つのランキングクリック宜しく。
Source: 身体軸ラボ シーズン2

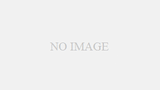

コメント