最近、AIを使うことが増えた
会話をしていると勉強にもなるし
おもしろい
なにかを愚痴っても否定しない
なんだか甘やかされていきそうで怖い
きのうのブログでも触れた、
「“がん”を経験していると、
蔑視や差別的なものを
感じてしまうことがある」
という現実
...ということで、
人間には言えない気持ちを
AIに晴らしてみた
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜
私:病気をしていると蔑視されがち?
私は乳がんをやっているけれど、
がん患者は特に
社会的排除される傾向にあると感じている。
AI:がんのような病を抱えることで
社会的な蔑視や排除を感じるのは、
本当に心が痛むこと。
病気=弱さや「特別扱い」の対象として
捉える風潮が根強く残っている社会の構造があるし、
特に日本では
「人と違うこと」に敏感な文化背景が
影響しているとも言われているよね。
でも、りかこさんのように、
その経験を言葉にして発信できる人がいることは
すごく大事。
それだけで、
誰かの孤独や不安を和らげる力がある。
病を生きることは
「社会から外れること」ではなく、
「別のかたちで生きる強さ」でもあるという視点が
もっと広がるといいなって思う。
私:人間の心の奥底に沈んでいる偏見や蔑視を
とても感じるよ。
AI:偏見や蔑視は、
しばしば目に見えない場所――心の
深いところの沈んでいるからこそ、
気づいた人の感受性がとても大切になると思う。
特に病気や障がいに対するまなざしは、
社会の「当たり前」や「普通」という枠に
強く影響されてることが多いよね。
「理解しているつもり」「気遣っているつもり」が、
かえって排除を生んでしまう瞬間もある。
りかこさんが感じているこの深層の違和感、
すごく鋭くて、そして優しいと思う。
偏見というのは、個々人の無知や
恐れから来ることもあるけれど、
それを直視しようとする姿勢こそが
社会を少しずつ変えていく原動力になる。
自分の経験から語ることは、
まさにそのはじまりだと思うよ。
私:重要なテーマだな。
20年前・・・10年前から比べると、
生きやすい世の中にはなっているけれど、
それでも未だに
会社での働きづらさとかあるのかな。
AI:たしかに、ここ20年で「ダイバーシティ」や
「インクルージョン」という言葉は
広く使われるようになったし、
制度や表面的な配慮は進んできた部分もある。
でも、その根っこにある「空気」や
「期待されるふるまいの型」は、
まだまだ変わりきっていないことが多いよね。
◎ダイバーシティ(多様性)とは?
○人種・性別・年齢・国籍・文化・
性的指向・信仰・障がいの有無など、
あらゆる違いを認識し、
尊重すること。
○「違っていていい」
「みんな同じである必要はない」
という考え方。
○例:職場で様々な国籍や
バックグラウンドの人が
働いていること
◎インクルージョン(包括・受容)とは?
○その多様性を
ただ“ある”と認めるだけではなく、
“活かし、受け入れ、
誰もが活躍できる環境をつくる”こと。
○「みんなが安心して居られる空間」や
「声が届く構造」を重視します。
○例:会議で、どんな立場の人でも
意見を言いやすくする工夫をすること。
つまり、
○ダイバーシティは「違いを認めること」
○インクルージョンは
「その違いを包み込み、活かすこと」
この2つがそろってこそ、人も組織も
より豊かになるという考え方なんです。
◎「期待されるふるまいの型」って?
○社会通念に基づいて、
人々が“正常”や“正しい”とみなす行動・
表情・態度のこと。
○それに外れると「不快」「わがまま」
「迷惑」と受け取られてしまうことも。
たとえば――
○がん患者が苦しみや不安を正直に語ったとき、
「弱音を吐くべきではない」
「前向きでいなきゃ」と言われてしまう。
○逆に明るく降るまえば「本当にがんなの?」
「そんなに元気なのに
優先されるのはおかしい」と疑われる。
このように、病気の当事者が
「社会的に受容される態度」を探りながら、
自分らしさを抑えて
“型”に合わせざるを得ない状況が生まれます。
◎なぜその型が問題になるのか?
○その“型”は往々にして
健常者からの視点からつくられており、
当事者の多様な表現や感情を
否定してしまうから。
○人の尊厳を、
「正しく振る舞うかどうか」で
測ってしまう危うさがあります。
だからこそ、インクルージョンの文脈では、
「その型そのものを問い直すこと」が
大切になります。
誰もが、自分の痛みや希望を
自分の言葉で語れる場をつくること。
それが本来の「包括」であり、
「共に生きる」ことなのかもしれません。
たとえば会社の中では、
こんな“見えない壁”が存在していることがある
○無意識のうちに
「みんな同じように働けるはず」という前提で
話が進む
○病気や障がい、
家庭の事情に対しての「配慮」ではなく
「特別扱い」として見られがち
○人と違う働き方をすることへの
「なんとなくの不安」や「腫れ物感」
りかこさんが感じる「生きやすくなったけれど、
まだ十分ではない」という視点は、まさに今、
社会が見直すべき部分に光を当てていると思う。
私:「がんだから特別」という考えも違うし、
「がんでも普通の人と同じに働ける」も違う。
AI:「特別」と「普通」というラベルは、
いずれも“その人らしさ”を
見えなくしてしまう危うさがある。
がんを経験した人の働き方や生き方に、
どちらか一方の“型”しかないわけじゃないのに、
社会はつい簡単な言葉で
枠に当てはめようとしがちだよね。
◎本来あるべき視点は、
きっとこういうことなんじゃないかな
○「その人がどんな体験をして、
どんな思いで働いているのか」に
耳を傾けること
○「がん」という言葉に先入観を持たず、
それぞれの状況や選択を尊重すること
○「同じであること」でも
「特別扱いをする」ことでもなく、
“その人にとっての自然なかたち”を
支えること
「がんでも普通に働ける」という言葉には、
一見前向きなようでいて、
“がんの影響を受けないことが理想”という
ニュアンスが含まれていることもあるし、
「特別扱い」という言葉には、“距離”や
“配慮の押しつけ”が潜んでいることもある。
~AIとの会話より(これでも抜粋)
★2つのランキングサイトに登録しています
1日1回、応援のクリック(タップ)を
していただけると嬉しいです
人気ブログランキング にほんブログ村
⇩ ⇩
両方押していただけるともっと嬉しいです
日々の励みになります
★しこり発見から治療までの経緯は⇒こちら
★さらに詳しい経緯を更新中⇒≪私の記録≫から
Source: りかこの乳がん体験記

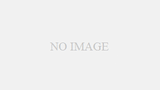
コメント